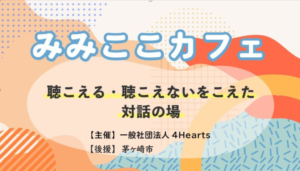ろう者が英語を学ぶとき(1)
~聴こえない私の聾英語教育への挑戦~

はじめに

現在では、新生児スクリーニング検査で、早期に聴覚障害があることがわかりますが、私が生まれた当時はそのようなテクノロジーがまだありませんでした。多くの聴こえない人がそうであったように、私も聴覚障害の発覚が遅れました。
私の耳が聴こえない理由は、長い間、はっきりとはわかりませんでした。生まれた時に仮死状態だったことが原因ではないかと聞いていましたが、何年か前に遺伝子検査をしたところ、ろうの遺伝子(先天性難聴の原因遺伝子)があることがわかりました。仮死状態で生まれたことと、耳が聴こえないことには関連性がないことがはっきりし、親が感じていた責任のようなものから少しは解放されたのではないかと思いました。
また、私は小中高から大学院まで、インテグレーション(聴こえる人と一緒に学ぶこと)の教育環境で育ちました。親が「ろう者」という言葉を使わなかったので、「重度難聴」という表現を私も使ってきました。「ろう(Deaf)」のアイデンティティは、アメリカでの学びから得られたものです。
本稿では、私の幼少時の様子から、就学を経て、学校での学び、そしてろう英語教育との関わりまでのエピソードの記憶や思いをたどっていきます。私の聴こえない人生での体験が、聴こえない子どもたちのロールモデルとしての一助となれば幸いです。
文字マグネットで話す子
「子どもの様子が何かおかしい」ということに親が気づき始めたのは、私が3歳ごろのことでした。「言葉が遅い」、「お話ができない」と分かっていても、親は、子どもの発達を信じて待とうとするものです。それは、「明日にでも話してくれるようになるかもしれない」という希望があったからでしょう。
当時の私は、声で話すことができなくても、おもちゃの50音マグネットとホワイトボードを使って意思疎通ができたそうです。それは3歳より前のことで、「話せないのに言葉が分かる赤ちゃんがいる!」と近所では有名になったということでした。私が声を発しないので、文字マグネットを使いながら、一生懸命「これは『あ・い・う・え・お』だよ」と親が教えていたのでしょう。たぶん私は、これを言われたらこれを出すというように、親の期待に応えようと、何らかのキューを読み取り、マグネットを取って出していたのかもしれません。
いつまで待っても話すようにならない私を、両親は辛抱強く待っていたようですが、近所の人たちから「病院に連れて行って検査してもらったほうがいい」と客観的なアドバイスを受け、とうとう大学病院めぐりを始めたのでした。私が断片的に覚えている大学病院での検査のシーンを話すと、「よくそんなことを覚えているね」と親は驚いていました。
たとえば、大きなビルの窓から外を眺めていたこと。しんとした部屋で台に乗って、上から大きな全身用レントゲンの機械が下りてきて、押しつぶされるのではないかと怖かったこと。薄暗いオレンジ色の光が灯る検査室で、冷たい吸盤をペタペタと身体のあちこちに付けられて、脳波検査を受けたこと。私の覚えている病院めぐりの風景です。
そして最終的に、私に聴覚障害があることが分かったのでした。
親としては、聴覚障害とは思っていなかったそうです。返事をしないけれど、話をしないけれど、マグネットを使って意思疎通ができているし、手足も動きます。笑いかければ笑い返すし、好き嫌いもはっきりしています。「話すのは遅いけれど、まさか聴覚障害だとは思わなかった」と、たいそうショックを受けたそうです。新生児スクリーニング検査がない時代なので、聴覚障害があることは3歳を過ぎるまではっきりとは分からないままでした。
補聴器を初めて着けた日
聴覚障害がわかり、訓練の日々が始まりました。ろう学校で訓練を受ける方法もありましたが、結果として民間の聴能訓練センターに通うことになりました。
補聴器を初めて着けた日のことは、なぜか覚えています。私に初めて音が入った日です。言語聴覚士の先生が補聴器のマイクに向かって「あーあー」「聴こえていますか?」などと話しかけるのですが、とても大きな音が突然入ってきて、私はフリーズしてしまいました。そして、うるさいと感じたので、正しく言えたかどうかは分かりませんが、「うるさい」と言ったように記憶しています。私に反応があったことで、先生や親が「聴こえた!」と安堵していた風景が、今でも脳裏に浮かびます。

幼稚園に通うようになってからは、週に1回か2回、通園をお休みして訓練の方に行く日々が始まりました。訓練は、多くの聴覚障害児が経験してきたように、決して楽しいものではありませんでした。今でも私の心にフラッシュバックしてくるのは、親に課された課題がこなせず、精神的に追い詰められていた母の姿です。
ある週末、母は画用紙に何か絵を描いていました。母はとにかくイライラして、絵を描いては失敗したとやり直していました。そして、とうとう私に「集中できないから外に遊びに行って。お昼まで帰ってこないで」と言い、私はさっそく近くの公園に木登りをしに行きました。木登りをしたり、すべり台で遊んだりして、そろそろおなかもすいたので帰ってきたら、母はまだ絵を描いていました。
翌日が訓練日でした。訓練の先生の指示で、子どもたちは絵を持ってめくりながら、何かを話しています。母に「私はどうするの?」とたずねましたが、母は怖い顔をして答えてくれません。とうとう私の番になりました。「私はどうするの?」と再び母に聞くと、「絵を見て思ったことをお話しなさい」と言うのです。私は何枚かの画用紙を持って立ちました。練習もしていなければ、絵の意味も聞けていないのに、です。「これは夕日です」「海です」「女の子です」と絵の説明を始めましたが、ストーリーを作ることはできず、助けを求めて先生の方を見たら、「うん、いいね。おわり。はい、拍手」と打ち切ってくれました。
家に帰ってから、母に「お母さんひどい。わからなかった。〇〇ちゃんも〇〇くんももっとたくさんお話できた。私できなかった」とわんわん泣きながらこぶしをぶつけたら、母も「ごめんね、お母さんが悪い。イライラして何も考えられなかった」と泣いていました。
後に教職についてから、当時の母の姿を何度も思い出しました。絵を描いていたのは、架空の物語を作り、絵を見せながら話すという課題が出されたからなのでしょう。発表の場では、宿題をこなしてきた親たちに囲まれて、母もいたたまれなさを感じていたに違いありません。発音訓練のために、親自身が多くの時間を犠牲にしなければならなかったことに、心が痛みます。

(著者)
秋山なみ
大阪生まれ
精神保健福祉士と英検1級の資格を持つ。
神奈川県にある聾学校で15年間、中・高等部で英語教育に取り組む。
2021年に退職し、現在は京都で手話の普及に関わる事業に携わっている。
趣味は社交ダンス。