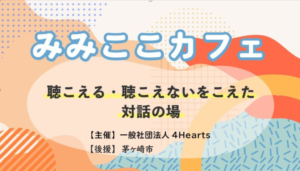難聴と私 ~「わかる」という感覚をもう一度~いつか手話で感じたい

聞こえにくさに気づいたとき
私は40歳の頃、急に耳の聞こえにくさに気がついた。それは、それまではっきり聞き取れていた父の声が聞き取りにくくなった時である。
私は実家近くにある、評判の良い耳鼻科で聴力検査を受けた。結果は聴者の60%の聴力、音域によっては80%くらいあるから、まだ補聴器をつけなくても日常生活に支障はないだろうと医師から言われた。
そこで私は、医師にどうして悪くなったのかと聞いてみた。自分では30歳代で何度か罹った滲出性中耳炎がその原因ではないかと思っていた。
ところが意外にも医師から言われたのは、「遺伝性だろう、子供の頃から悪かったんじゃないかな」という言葉だった。
そう言われてみれば、子供の頃、音楽の調音と英語のヒアリングが人よりうんとできなかった。 才能がない上に努力不足と自分の中で勝手に完結させていた。音楽は大好きだったけど、その道は諦めた。英語のいらない世界で頑張ろう、と決めていた。
そして、40歳になって初めて、「貴女は難聴だったんですよ」と言われた。
どうだろうか。
子供の頃に難聴と言われるのと、40歳になってから言われるのと、違いはあっただろうか。
子供の頃に言われていたら、母ががっかりし心配して、少しでも良くなるようにと思案しただろう。それは、子どもの私にとって、しんどいし、きつかっただろう。
40歳になった私から聞いた母は、「あら、そうなの。」と、驚くほどあっけらかんとしていた。
それから7・8年は困らなかった。聞く必要のあるものはちゃんと聞こえていたような気がする。有名な講師の講演会にもよく出かけた。その頃のノートには、びっしりとその内容が書き留められている。
ただ時々、人と話しているときに眠くなって寝てしまうことがあった。それは、込み入った悩みの話だった気がするが、途中で分からなくなって、聞こえなくなってしまうのだ。
これは私の誠実さが不足しているせいだと何度か反省したが、失った友達も何人かいる。長男に、「そんなことで失うくらいの友達はたいしたことないよ」と言われて、そういうものなのか、と納得した。
47歳になった頃、PTAや自治会等、20~30人の集まる話し合いの場で、人の話が聞き取れない、分からない、それが原因で仕事にならない、という状態になり、初めて補聴器を付けた。
まだアナログの補聴器だったが、かなり楽になった。その時、右耳も左耳も同じくらいの聴力だったが、なぜか左の耳にだけ補聴器を付けた。どうして両耳にしなかったのか記憶にない。片耳でも高価なものだったからだろうか。
補聴器を付けていない右耳は、人と話すときには役に立たなかった。
それからは、左耳だけが私のコミュニケーションの架け橋になった。人と話すときには、耳が聞こえにくいと告げて、左耳の方から話してもらった。何度か聞き返すこともあったが、なんとかなった。
ただ、まだ50歳前の私が、耳が悪いと言うと、人によってはあからさまに早い老化を笑う人もいた。同年代の人もだが、高齢者にはもっと理解してもらえなかった。
今、その頃を思い起こしてみるとそれは当たり前で、私自身が自分の難聴をよく理解していなかったのだ。相手にどうしてもらえば、少しでも人の話が聞こえるのか、自分にもよく分からなかった。
使っていない右耳のことが気になって、できれば聞こえているふりをして通したかった。

また、その頃、両耳に耳穴式のアナログ補聴器を入れてみた。でもそれが大失敗だった。自分の声が耳の中でこもり、ハウリングや風切り音ばかりが大きくて、聞きづらくて疲れた。
当時私は、子供たちにお話を語る、ストーリーテリングというボランティアをしていたが、この補聴器のせいで10年続けたこのボランティアを辞めた。耳の中に声がこもると、自分の声をどれくらい出せば、子供たちに届くのかが、分からなくなったからだ。
子供のおしゃべりが聞き取れなくなって、対応できなくなったのも辞めた理由のひとつだ。
この経験で、補聴器を選ぶのは難しいと知った。高いものだからそう簡単には買い替えられない。結局、この具合の悪い補聴器で何年か我慢した。
そのうち、右耳の方の補聴器が全然働いていないような気がしてきた。壊れているのでは、と思った。ちょうどその時、茅ヶ崎タウンニュースで補聴器センターの記事を見た。すぐにそこへ行ってみた。そこには多田さんという補聴器のスペシャリストが居た。
右耳の具合が悪いと告げて、聴力検査を受けた。補聴器のせいではなかった。
私の右耳にはもう聴力が無かったのだ。
「え~~!一体いつの間に!!」
補聴器というのは、聴力の残っている耳に付けると効果があるが、聴力の無い耳に付けても聞こえるようにはならないそうだ。
この時、聴力の残っている左耳にデジタルの補聴器を調節してもらった。聞こえは、風切り音や、音が耳の中にこもることもなく快適になった。もう少し早くこの補聴器に出会いたかったなぁ。
一方で、右耳の聴力が無くなったことは、私にとってつらいことだった。確かに聴力があったはずなのに、このままだと左耳だっていつかは聞こえなくなるかもしれない
この頃、私には4人のママ友がいて、よくランチをし、旅行にも行った。5人の輪の中で一緒に話しを聞くことはできなかったが、一人ひとり対面では話ができた。みんな少しずつ声が大きくなって、私たちの周りはうるさかったが、ありがたかった。
この仲間に、私は右耳の聴力がなくなった事を話した。
するとその中の一人に、「あなたは聞こえない自分のことばかりかわいそうみたいに言うけど、聞こえない貴女と一緒にいる者の居づらさを考えたことがあるの」と言われた。彼女には、日頃から私の能天気な性格を自分勝手だと指摘されていた。
自分の不誠実さを少しずつ誠実に変えていくことはできるかもしれないが、聞こえなくなった聴力を取り戻すことはもうできない。
そう思うと、自分の感情以上に、目から涙があふれて出てきて止められなかった。これは15年くらい前の出来事だが、この時の彼女とはそれからもいろいろあって絶交した。
でも、その時の彼女の発言を私は決して無駄にはしたくない。どんな状態にあっても、自分と一緒にいてくれる人への感謝と思いやりを忘れてはいけない。

書道教室と家族
私は2008年から自宅で書道教室を始めた。
30歳のときからプロになりたくて始めた書道だが、少しずつその夢を実現していった。
最初は10人足らずだった生徒たちは、今では50人近くいる。大人の方も15人ほど、10年以上辞めずに続けて下さっている。本当にありがたい。
教室で教えることは割と一方的な仕事で、聞こえなくてもあまり困らないし、初めて教室に来てくれた親子には必ず耳が聞こえていないと伝えて、連絡はすべてメールでお願いしている。
教室での筆談も生徒には勉強のうちの1つだからいいんじゃないかと次男が言ってくれた。
書道は、耳が悪いから選んだのではなく、好きだから、いくら書いても飽きないから選んだ仕事だ。
書道教室が少しずつ軌道に乗ってきた2011年に、母が脳梗塞であっけなくこの世を去った。 父がひとり、神戸の実家に残された。
父は、2度の胃ガンの内視鏡手術を受けていた。その後遺症なのか、食事がうまく取れなくて65㎏あった体重が、10年で15㎏も落ちてガリガリだった。それでも姿勢が良くて、杖をつくこともなくシャンとしていた。
母は父に食べさせることでいつも苦労していた。その上、父の気難しくて思いやりのない性格に、うんざりしていた。母は父より長生きして、余生を楽しむつもりだった。
父は、長年あらゆる思い出を共にしてきた母を失い、「とうとう天涯孤独になったなぁ。」と漏らした。父は神戸の家から離れようとはせず、ひとり娘とその息子2人には頼らないと考えていたようだ。
それから3年間、要支援2の父はヘルパーさんに週2回食事を作ってもらい、一人暮らしを全うした。私も月に一週間は神戸に帰った。父は亡くなる2・3ヶ月前から、入退院を繰り返した。できれば、自宅で死にたかったんだと思う。
それを叶えるためには、私がやっと、仕事の基盤が出来かかった書道教室を放棄しなければならなかった。
何度も迷ったが、私は自分の仕事を守った。
病院から自宅に帰った父を介護するときに一番困ったのは、父の言葉が聞き取れないことだった。弱っている父の声は小さく、筆談を求めるのも憚った。
何度か聞き取れないことを繰り返していると、ある日、父が大きな声で「なんで聞こえんのや!!」と怒鳴った。
それは自分の娘の障害を悔しがるような叫びだった。
「なんでって言われても、聞こえんもんは聞こえんよ。」と私は小さな声でつぶやいた。耳が達者な父にはきっと、私の小さなつぶやきも聞こえたと思う。
この頃、私は、「みんなの手話」を見ていた。手を動かしながら話している私を見て父は「何をしとんや。」と言った。それは、私に訊いているのでは手話をやってみたいと思ってなく、「そんなことをするな」という意味の言葉だった。
父には聞こえない人に対する強い偏見があるのだと知った。
母が亡くなってから、父と過ごした3年間は決して大変なことばかりではなかった。
でも、この時のことを今でも何度も思い出す。
今年、7回忌を迎えた。
私は「口話法」という言葉を知らなかった。ろう者の言葉である手話を禁止して、聴者の言葉を使えるようにする教育だが、そんな話は明治・大正・昭和の初めのことだろうと思っていた。
まさか、戦後その教育方針が主流で、ろう者が手話で学ぶ権利はやっと2008年頃から認められたものだったと知ってびっくりした。
那須かおりさんもこの歴史の真中を生きた人で、大変な努力をして口話を身につけられたそうだ
朝鮮半島の人々が日本に連れて来られ、改名させられて、母語を奪われた歴史とまるで同じじゃないか。同じような過ちを歴史は何度も繰り返すものなのかと私は怖くなった。
手話の学校と難聴のディレクター ――ETV特集「静かで、にぎやかな世界」制作日誌 (ちくま新書) 新書 – 2021/1/8 長嶋 愛(著)
NHKのディレクター長嶋愛さんの著書『手話の学校と難聴のディレクター』(ETV特集「静香でにぎやかな世界」制作日誌)を読むと、ろう者の子供にとって手話がどれほど大切な言葉かがよく分かる。耳が聞こえなくなった私にとっても、この手話がこれから私の命綱になるかもしれない。
2020年の転機
2020年、この年はコロナで始まって、まったく収束しないまま2021年を迎えた。オリンピック・パラリンピックは延期になった。次男の結婚式も延期になった。
私にとっても、大きな転機の年になった。
父が亡くなって6年、その間に私の聴力はますます落ちて、補聴器を2段階グレードアップした。
もう以前のように人とは話せない。友達との話もほとんど内容がわからず、一緒に居ながらポツンと一人のような気分になった。
友達がそのことに気がついて、時々筆談をしてくれた。本当は全部書いて欲しいが、それは言えない。少し書いてくれるだけでも、少し嬉しい。
2人の息子はそれぞれ結婚して、長男には娘が生まれ、家族が増えた。特に、次男のお嫁さんが来てからは家族の会話がにぎやかになった。家族は皆、よくしゃべり、よく笑っている。
でも、私にはまったく話の中身がわからない。家族は皆、私にはおかまいなしだ
私の方も、あんまり愛想が悪いのも失礼かと思って、時々笑ったりするから良くない。みんなは、私が聞こえていると思っているのかもしれない。話の内容は聞こえないからよく分からないけれど、たわいのない話らしい。
隣で笑っている夫に、何の話かと聞いても、わかりやすくはっきりとした回答が返ってきたことがない。
何をこの人たちは笑っているんだ。
子供たちには腹が立たないが、夫には腹が立つ。この世で一番近くて、一番遠い人。
2020年茅ヶ崎版タウンニュース8月28日号「人物風土記」に那須かおりさんが紹介されていた。
神戸出身、聴覚障害者、人工内耳…。
ものすごく魅力的な人に違いないと、直感で思った。阪神大震災も経験しているだろうと思った。
『2020年10月11日(日)みみここカフェ第1回目』
ネットで調べてすぐに申し込んだ。この日が楽しみで仕方がなかった。誰の紹介でもなく、自分の直感だけを信じて、新しい世界に入っていくことはめったにない。
なのに、不安もあまりなかった。
当日、初めて行く場所だったので、早めに家を出た。案の定、どのビルかすぐにはわからなかった。でも、なんとか時間までに無事到着。
知らない人ばかりなのに、居心地が良かった。音声認識用のパソコンが私のために用意されていた。
ろう者、車椅子の人、精神疾患のある人、聴者、手話がわからない難聴者は私ひとりだった。音声認識の文字を通してだが、人の話が100%わかる体験を久しぶりにした。
人の意見、人の話を聞くと、すぐに自分の言葉が湧き上がってくる。人の話を聞いて私が話し、私が話すとまた別の人が話す。
なんて楽しいんだ!

2時間はあっという間に過ぎた。私のために準備された「情報保障」に私は驚いた。
そもそも「情報保障」という言葉も知らなかった。
「音声認識」、こんなもの(これ)があるなら、まだまだこれから色んな事に挑戦できると思った。友達との会話で使ってみよう。家族との会話でも使ってみよう。書道教室でも、これを使って生徒の話を聞いてみよう。
そうすれば、今までどうにもならなかったことが、全部うまくいくと思った。家に帰ってすぐに、夫に伝えた。自分では探せないけど、夫になら見つけられるだろうと思った。
半年近くかかって、やっと1つの音声認識アプリを見つけてくれたけど、友達の会話にも使えない、家族との会話にも使えない、夫の言葉でさえちゃんと訳せない。
がっかりした。
でもそのうちきっと、性能のよい音声認識が生まれて、私の望みを叶えてくれるに違いないと思った。
このころやっと、自分は聞こえない人として生きようと腹をくくった。
カッコウつけて聞こえるふりをしたり、つくり笑いをするのはやめようと思った。はっきりと私は聞こえないと伝えて、筆談してもらおうと決めた。聞こえない自分を、自分が受け入れて、生きていく覚悟ができた。
今でもすぐに、聞こえないふりをしてしまうけれど…
もう、本当に聞こえないのだから。
那須さんに紹介してもらって、難聴者手話勉強会に入った。そこには私と同じ難聴者がいた。私が声で話すと、聞こえない、わからないと言う仲間がいる。
筆談したり、手話をしたり、ひっちゃかめっちゃか…
だけど、同じ気持ちを共有できる人たちがいる。
とてもうれしかった。
今の私の目標は、手話で人と話ができるようになることだ。筆談や音声認識を介さずに。自由に話せて、相手からも言葉が返ってくる。言葉を自力でキャッチする。
耳で聞く言葉を失った私に残されている最後の言葉、それが手話。
「わかる」という感覚を、私は取り戻したい。

(著者)
岩浪由美
1956年神戸市に生まれる。
現在茅ヶ崎在住。40歳頃に遺伝性の感音性難聴の診断を受ける。補聴器をつけながら過ごすも、50歳頃に右耳失聴左耳にのみ補聴器をつけて生活。
ここ10年の間に3度補聴器を替えて今では一番高機能の補聴器をつけているが、それでも普通の会話が困難な状態。
筆談をお願いしている。
必死になって手話勉強中。
自宅で書道教室を営んでいる。書道があってよかったと思える人生を一人ひとりにプレゼントできればいいなぁと思ってやってきた。
耳の聞こえが悪くなってから少しずつ生きづらさを感じていたが、
一年前に那須さんに出会ってから新しい時間が広がり始めている。聞こえなくなってもたくさんの友達と語り合いながら、自分にこんな生き方があったなんて想像もしてなかったなぁといえる人生を生き抜きたい。